「あいつはモノの考え方がおかしい」
という見解はそもそも成り立たない。
なぜなら「見解の相違」で満足する人間などほとんどいないからだ。
ホームレスに施しをするかどうか。
人工中絶を許容的に支持するかどうか。
鳩山政権を支持するかどうか。
エクソシストをどう評価するか。
パソコンを数か月に一度買い換える電電は浪費家なのか(笑)
いかにも見解の相違とやらが現れそうな議題をあげてみた。
一つ一つに関してここで私の見解を述べることはしない。
人によって意見がさまざま出るであろうことが予想できればここではよしである。
重要なことは「人によって意見が違う」という事実を受け止めることではない。
その人の意見がどのパラダイム(視点)に基づいて、どのような解答方程式が構築されているか、である。
人が持つデータとその分散具合が各々違う以上、
各人が持つ解答を導くための方程式が変わるのは至極当然である。
そこまで知っていながらまだ理解できない人はいる。
「あいつは俺が持っているデータを持ってないからそんなくだらない見解になるのだ」と。
では自分は「あいつ」がもつデータを持っているかといえば、持ってはいない。
単に自分と比較して欠落部分を抽出したにすぎない。
これは依然ブログでも出したネタではあるが再度掲載する。
この「自分が知っていることは相手が知ってて当たり前」的な思考回路は
幼少期の人間がもつ特徴の一つであり、
自分が相手より判断データが多いことで優越感を持つことは「頭が幼い」ことに他ならない。
数年前からの情報化社会の波によってその傾向が顕著になったように感じる。
情報は鮮度が命。
情報は正確さが命。
情報はバリエーションが命。
確かにそうだろう。
がしかし、自分が満足するほどそれらの情報を得ることは難しい。
しかも人間はお互いの持つ情報の並列化さえ満足に行うことが出来ない。
最も意識すべきことは、個人が持つ解答方程式がどのような意味を持つか考察することである。
ここで具体例をあげよう。
ライオンの数はどう増えるのか。
食物連鎖の見地から小学生でも知っている内容ではあるが、
ひと昔前の生物学者、動物学者たちは真剣に悩んでいた。
一人の学者は、一匹のライオンが生む頭数を考えた。
一人の学者は、全体数が年ごとにどう変化するかを考えた。
一人の学者は、ライオンが死ぬ原因を考えた。
結果として、「ライオンはそのうち絶滅する」「ライオンが世界を支配する」
などといったまちまちな意見ばかりが生まれてしまう。
がしかし、その意見の一つ一つはある意味ちゃんと筋が通っていることに注意だ。
全体数の推移を調べた学者は、少しずつ減っていく傾向に目をとめ
このまま減っていけば何年後に絶滅するかを予測した。
ライオンが食物連鎖のトップであることを知った学者は、
ほかの動物を食べつくせば世界の頂点に立つと予測した。
実際には増えたり減ったりを繰り返しながら、平均的な数はあまりかわらない。
もちろん絶滅危惧種であればその平均的な数字が減少傾向にある。
どんどん増えると考えた学者は年と頭数が比例するという単純な解答方程式を作った。
絶滅すると唱えた学者も同様。
実際には餌の多さによってある程度の頭数でライオンは頭打ちになるのだ。
結局熾烈な縄張り争いと相まってライオンは減少していく。その繰り返し。
その場その場のデータと自分の見解をマッチングさせてもさほど誤差は出ない。
自分が作ったその解答方程式が過去、未来でも同じようなことが言えるかどうかまで
考察することができなければ、まるで使い物にならないであろう。
そういった意味で、人間が日々アップデートするべきは
新しい情報に加えて、新しい解答方程式なのである。
対戦相手にとっては一撃を入れるチャンスであるが、
ここで迷わず一撃を入れる勇気があるかどうかが分かれ目である。
なぜならば攻撃に転じてしまえば、相手のスキがフェイクだった場合に
一気に不利になってしまうからだ。
そしてその不利な状況は一瞬にして敗北へとつながる。
反撃が怖いのだ。
上級者が伸び悩む一因としてこの「一撃のためらい」があるという。
格闘の仕方がわかってきただけに、その知識と経験が拳を遅らせる。
我々の生活においてチャンスなどはいくらでも転がっているが、
その多くはカウンターパンチとしての反撃力を持っている。
告白のチャンス→NOだった場合に今の関係すら気まずくて続けられない恐怖
昇進のチャンス→責任という両肩にのしかかる重圧に対する恐怖
まだまだいくらでも例はあろう。
そういった意味で人間は現状維持が好きなのである。
チャンスは多くの場合一瞬である。
しかしながらここに多くの誤解がある。
チャンスが一瞬で逃げてしまうのではなく、
自分が一瞬で逃げ腰になるのである。
チャンスは逃げない。
ドラえもんの秘密道具に「リアルキャップ」ってのがある。
この帽子をかぶって妄想すると、妄想したものが目の前に現れる!
という道具。
もちろんそれは幻で、本人にしか見ることができない。
本編においてのび太はこの帽子でスネオに対抗すべくラジコンを出す、というストーリーだ。
ここで二つの問いを読者に考えてもらいたい。
まず一つ。
誰でもいいから身近な人を思い浮かべて下さい。
その人は「存在」するだろうか?
現れたと同時に消滅してしまうような脆い物質、
それは果たして「存在した」と言えるだろうか?
一つ目の問いの答えはおそらく「Yes」だろう。
二つ目は意見が分かれるかもしれないし、
設問にそもそも問題があると言われるかもしれない。
この問いの答えそのものにさして意味はない。
人間が「何かの存在」を確実視するための要素がいかに不安定か、
ということが言いたかったわけだ。
ここで人間の心理に面白い特徴を見出すことができる。
「疑わしくなければとりあえず無意識に信用し、現実的な存在感を持つ」という特徴だ。
たとえば、シーラカンスの存在を疑わなくても、ツチノコの存在を疑う、といった場合。
両方とも実際に見たことがないにも関わらずここまで印象が違うのはなぜか。
シーラカンスもツチノコも写真は出回っているではないか。
しかしながら決定的に違うのは、その写真の出どころである。
シーラカンスは生物系科学雑誌に掲載されるのに対し、ツチノコは都市伝説雑誌等に掲載される。
つまりシーラカンスの存在を信じているのではなく、
シーラカンスの存在を述べる人に対し「疑わしくない」という印象があるだけなのだ。
すこし視点を変えてみよう。
ここで読者に再度考えてもらいたい。
「色」は存在するだろうか?
少しでも物理学に通じる人であればこの問いの意図をわかって頂けるかと思う。
結論から言うと、色は存在するとも言えるし、存在しないともいえる。
本来色とは、光の持つ特定の波長に対して人間の視神経が反応した結果、脳内に情報として受け取られる。
リンゴに白色光が当たると特定の波長だけが反射し目に入る。
その特定の波長の光を人間は「赤」と判断するわけだ。
要するに「色」という概念は人間の脳の中にしか存在しないってことだ。
現実世界では光を反射する物質の違いが存在するのみである。
同じように遠近感というものも人間の脳の中にしか存在しないが、
左右の視界差からそれが現実的だと思ってしまいがちだ。
人間は一度現実感を持ってしまった情報を疑うのが苦手である。
なぜならその現実感は無意識に形成され、なおかつ理論的でもなんでもないからだ。
最後に。
読者諸君、まず自分のフルネームを思い浮かべてほしい。
さて、それは本当にあなたの名前ですか?
発音の仕方や口の動きを意識して数分間自分の名前を呟いてみるといい。
ほら、疑わしくなってきた!
わかりそうでなかなかわからない。
「わかる=理解する」
ということなのであれば、
「理(ことわり)を解く」ということなのであろう。
「わかる」という単語そのものを自ら「理解」していなければ、
ありとあらゆることを理解することはできず、理解させることもできない。
新たな知識を理解することを想定するならば、
なぜ理解することが困難であるかを理解せねばならない。
自らにとっての新たな知識とは言い換えるならば
「陸の孤島」ならぬ「知識の孤島」「脳の孤島」である。
例えるならば、「非常識」は「常識」というカテゴリがなければ存在しえない。
ゆえに、一般にいうところの「非常識な人」というのは
自らの「識」が「社会的孤島」であることを理解せず、
理解しないがゆえにその「識」が自らにとっての「常識」たりえるのだ。
逆にいえば、「常識人」とはその常識そのものが「大きな孤島」と捉えることも出来る。
大きな「常識」が孤島になる可能性を秘めていることを理解せねば、
「非常識」はただの「識の外」にしかならず「非常識」を理解することも出来ない。
実際に日本の技術をはじめ、多くの分野で「ガラパゴス化」が見られるというのは
ここに起因すると考えることが出来よう。
では「わかる」ために「知識の孤島」を脱することは可能だろうか。
個人レベルでそれを達成することはさほど困難なことではない。
そのためには孤島を理解し、孤島が孤島である理由を理解すればよい。
孤島は孤島であるがゆえに自らを評価することが困難である。
自らが長身であるかどうかは他人と比較せねば評価できない。
評価して初めて、自らが長身であることを理解できる。
その時点で自らの知識が「長身」というカテゴリとの交通網を確立できる。
いつしかそのカテゴリは自らの知識に内包され、年月を経て孤島へと変貌を遂げる。
密林の奥地に住む先住民達にブログを理解させることは至難の業である。
彼らにとってブログとは完璧な知識の孤島である。
ブログを家や狩猟の道具、雨や木で評価することが困難だからだ。
がしかし、家があるならば電話を理解させることは出来るかも知れない。
誰かと話をするために家を出ねばならないという面倒を解消する便利なものがあると。
もちろん通信や電気などをいちいち理解する必要などここにはない。
「家」「言葉」「仲間」といった知識があればなんとか評価することが出来るからだ。
電話が理解できればFAXも理解できるかもしれない。
FAXが理解できれば・・・
といったように、いくつもの知識の孤島へ交通網を作り
最終的にブログを評価するだけの交通網が完成する。
なぜ「わからない」という現象が生じるのか。
それは「理解したいモノ(孤島)」へたどり着くために、
どの孤島からどの孤島へと歩めば目的の孤島へたどり着くかが見えないからである。
いくつもの交通網を経て人間はモノを理解する。
「何がわからないかがわからない」といった現象は
どこか遠い孤島で道に迷った状態をいうのかもしれない。
「スカベンジャーロボット大会および大会向け製作教室!!」
http://circle.cc.hokudai.ac.jp/architect/
詳細はHP↑を参照ください。
まだまだ空いてますよ~
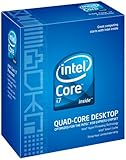
先ほどやっとインストールが終わりました。
まだいろいろとソフトを入れなきゃならないけどね。
ウィルス対策ソフトを入れたら遅くなるんだろうなぁなんて
思っていたけれど、なかなかどうして速いじゃないか!
現在の構成を簡単にまとめておこう。
OS:Windows7 Pro 64bit
マザボ:GIGABYTE EX58-UD4P
グラボ:ELSA Geforce9800GTX
メモリ:ノーブランド3GB
メインSSD:Transend 64GB
サブHDD:HITACHI2TB
電源:600W
まだネットは有線のままですが、
はやく無線にしないと家中を這い回るLANケーブルが邪魔になりそうだ。
そういや64bitOSに対応する無線LANってほとんどなかったんじゃ?!
なんて考えてたら、案の定一昨日バッファローから64bit対応版が出ておりました。
ビスタとも使い勝手が若干変わっているのですが、そこは慣れだろう。
一応XPモードを備えているとはいえ、
マニアックなソフトを仕事柄使うことが多い私。
はやいとこ仕事ができるところまで持っていかねば・・・
現在SAISという団体に所属しております。
簡単に言うと「わかる」をサポートする動画サイトの運営団体。
現在開発環境を構築中なのですが、
XAMPPやVertrigo等をいろいろ使ってます。
インストール最中にね、Portが空いてませんてなエラーを吐くわけですよ。
Portが占拠されてるらしくて、実際Portを調べるソフトがいろいろあるわけですが
なんとなく使い方がわからん(笑)
パソコンを再起動してやると、すんなりエラー回避できたので
おそらく余計なソフトを起動してたまま使ってたんだろうなぁ。
XAMPPに関してはこの再起動がききました。
なにせ、Portがあらかじめ占拠されてるとインストールすらできませんから。
ここら辺で困ってる人。
Skypeの設定もいいですが、再起動もお勧めです(笑)
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
北海道にロボットフィールドを作ろうと日々奮闘中。

